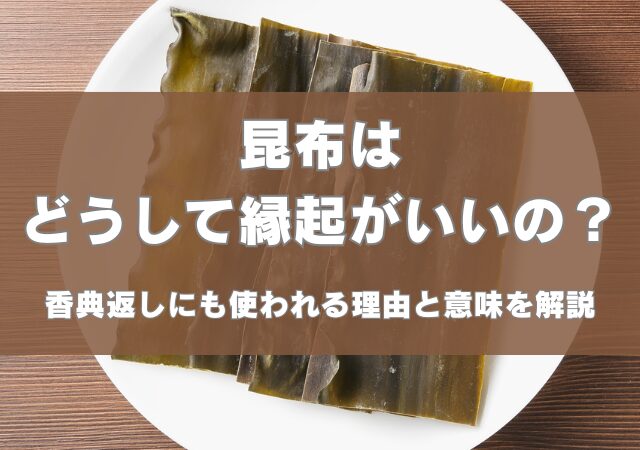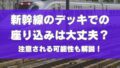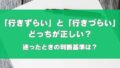お祝いごとや贈り物の場面で「縁起物」としてよく見かける昆布。
実は、お正月の昆布巻きや結婚式の引き出物・さらには香典返しにまで使われていることをご存知でしょうか?
一見すると慶事と弔事で使い分けが難しいように思える昆布ですが、古くから日本の食文化や風習に深く根付いた意味や由来があるのです。
この記事では、なぜ昆布が縁起の良い食材として扱われてきたのか・語源や背景に冠婚葬祭でどのように用いられているのかを詳しくご紹介します。
昆布の知られざる意味を知ることで、改めてその奥深い魅力を感じていただけるはずです。
昆布が縁起物として親しまれている理由

昆布が縁起の良い食材として古くから親しまれているのはただの語呂合わせだけではなく、その言葉に込められた意味や日本の風習・文化との結びつきが深く関係しています。
たとえば「昆布(こんぶ)」は、「よろこぶ(喜ぶ)」という言葉にかけられていて「幸せが訪れる」「うれしいことがある」といった前向きな意味合いを持ちます。
さらに古くは昆布のことを「広布(ひろめ)」と呼んでいたことから、「お披露目」や「披露宴」など慶事の場で使われる言葉ともリンクしてきました。
また昆布は海中で力強く成長し繁殖力も旺盛なため、「子孫繁栄」や「子宝に恵まれる」といった象徴的な意味も持たれるようになりました。
こうした背景から、昆布は結婚式などのお祝い事で引き出物として贈られる機会が多くなっていったのです。
ちなみに昆布と同様に縁起をかつぐ食材には「鯛=めでたい」「鰹節=勝つ」といった語呂合わせの意味があり、雄節と雌節から成ることから「夫婦円満」の象徴とされることもあります。
香典返しに昆布を選んでも失礼にならないの?

「昆布は慶事向けの縁起物」として知られていますが、弔事である香典返しとして昆布を選んでも差し支えはありません。
実際に多くの百貨店や返礼品専門店でも、昆布は香典返しの定番商品として取り扱われています。
そもそも昆布は仏事と深い繋がりを持つ食材で、精進料理に欠かせない存在であることからも分かるように供養や法要の場では自然な形で登場します。
さらにかつては香典そのものに昆布が使われていたという説も残っており、昆布と弔事の関係は決して新しいものではありません。
また、香典返しは「後に残らないもの」が良いとされる傾向があります。
これは「不幸を引きずらない」という意味に由来しており、食品のように消費できるものが選ばれる理由の一つです。
昔の葬儀では喪主が弔問客にたくさんの食事を振る舞うのが一般的で、その背景には「生きる者が食べることで死を乗り越える」という象徴的な意味もあったと考えられています。
こうした文化的な背景から参列者側が香典の代わりに食べ物を持参する風習があり、そこに昆布も含まれていたのです。
ただし「昆布はお祝いの場にふさわしいものだから弔事には避けるべき」という意見が全くないわけではないので、気になる場合は地域や親族の慣習を確認しておくと安心。
とはいえ現在では上品なパッケージの昆布製品も多く、保存性や軽さ・持ち運びやすさなどの点からも香典返しとして非常に実用的なので選択肢の一つとして覚えておくといざという時に役立つでしょう。
お正月料理に欠かせない昆布巻きの意味

おせち料理に登場する「昆布巻き」はお正月の定番料理として親しまれていますが、実はその一品にもたくさんの願いや意味が込められています。
昆布そのものはもちろんのこと、一緒に使われる食材にもそれぞれ縁起を担ぐ由来があります。
ここでは昆布巻きに使われる代表的な3つの素材について込められた意味や願いを詳しく見ていきましょう。
「昆布」は喜びや長寿を願う
昆布は「よろこぶ」という言葉にかけられ、新年に喜びの多い年を迎えられるよう願いが込められています。
また漢字で「養老昆布」や「子生(こぶ)」と書かれることから、不老長寿や子孫繁栄といった意味も持たせることができます。
こうした複数の縁起の良い意味が重なっているため、お祝いの席でよく使われているんです。
「かんぴょう」は結びつきと長寿の象徴
昆布を巻くために使われるかんぴょうにも意味があり、細くて長いその形状は「長寿」を連想させて巻いて結ぶことで「良縁」や「人との結びつき」を象徴しています。
さりげない素材ながら、幸せを願う気持ちが込められているのです。
「ニシン」は両親と子孫繁栄を表す
昆布巻きの中に入っているニシンは「二親(にしん)」とかけて、両親への敬意や長寿の願いが込められています。
またニシンはたくさんの卵を産む魚としても知られていて子宝や子孫繁栄の象徴でもあるので、家庭円満や代々続く幸せを願うおせちにふさわしい具材とされています。
昆布はあらゆる場面で使える日本らしい縁起物

昆布は結婚式やお正月といったお祝いの席はもちろんのこと、香典返しのような弔事においても用いられる非常に柔軟で意味の深い縁起物です。
喜びを表す「よろこぶ」という語呂合わせや古来からの呼び名である「広布(ひろめ)」に由来するお披露目の意味・さらには不老長寿や子孫繁栄といった願いも込められていて日本人の暮らしや行事と強く結びついてきました。
また香典返しとしても昆布は根強い人気があり、精進料理に使われるだけでなく保存性に優れていて重くないという実用的な面からも選ばれやすい贈り物。
近年では洗練されたパッケージの昆布商品も多く、上品な印象を与えられる点も魅力です。
お正月の昆布巻きに込められた「幸福」「長寿」「縁結び」などの願いからもわかるように、昆布は単なる食材ではなく想いを伝えるための象徴的な存在です。
冠婚葬祭や年始の贈り物に悩んだ時は、ぜひ昆布を選択肢の1つに加えてみてください。