料理の保存に欠かせないタッパーですが、たまに「タッパーがあかない…」という状況にイライラしてしまうこと、ありませんか?特に力を入れてもビクともしないときは、本当に困りますよね。
実は、タッパーがあかないのにはいくつかの理由があり、レンジで温めた後に冷めることでフタが密着したり、繰り返し使ううちにタッパーがわずかに変形してしまっていることもあるんです。
無理に開けようとするとケガの原因になることもあるので注意が必要です。この記事では、タッパーがあかない時に役立つ対処法を、家にあるもので簡単にできる方法を中心にご紹介していきます。
主におすすめなものは、以下の5つです。
-
スプーンやフォーク(フタと本体の隙間に差し込むため)
-
輪ゴム(フタに巻いてグリップ力を上げる)
-
ぬるま湯(フタ部分を温めて柔らかくする)
-
シリコン製の滑り止めマット(開けるときに手が滑らないように)
-
タオルや布巾(力をかけやすくするために包んで持つ)
記事で詳しく説明しますね。
なぜタッパーがあかないのか?その主な原因
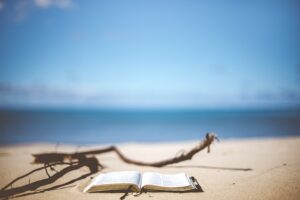
タッパーがどうしても開かないとき、焦って力任せに開けようとしてしまいがちですよね。でも、ちょっと待ってください。実は、タッパーが開かなくなるのにはちゃんとした理由があるんです。
まず一つ目は「密閉されすぎている」こと。タッパーの中が完全に密閉されると、内側と外側の気圧差でフタがぴったりくっついてしまいます。これが意外と強力で、指の力だけではなかなか開けられません。
二つ目は「変形や劣化」も原因のひとつです。長く使っているとフタや本体が少しずつ変形して、余計に開けにくくなることがあります。
三つ目は「中身の温度差による密着」。熱いものを入れてすぐにフタをすると、冷える過程で中が真空状態のようになり、フタが吸いついてしまうんですね。
タッパーがあかない時にやってはいけないこと
タッパーが開かないと、ついつい焦って無理やり開けたくなりますよね。でもそれ、ちょっと危ないかもしれません。
まず「無理やり開けるとケガの原因に」なります。固くなったフタを力いっぱい引っぱると、勢いで手が滑って指を切ってしまったり、腕をひねってしまうことも。
次に「フタや本体が破損してしまうリスク」もあります。プラスチックは意外と衝撃に弱く、割れたりヒビが入ったりしてしまうんです。特に寒い時期は素材が硬くなっているので要注意。
さらに「中身が飛び出して汚れることも」。開いた瞬間に勢いで中の汁物が飛び出すと、大惨事になります。無理に開ける前に、まず落ち着いて対処法を試しましょう。
家にあるものでできる!タッパーがあかない時の対処法
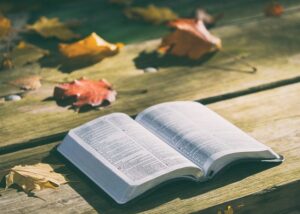
実は、特別な道具がなくてもタッパーを開ける方法ってあるんですよ。家にあるもので試せる方法をいくつか紹介しますね。
スプーンやフォークを使う
フタと本体の間にスプーンやフォークの先をそっと差し込むと、てこの原理で少しずつ持ち上げることができます。このとき、角度をつけすぎたり力を入れすぎると、プラスチックが割れてしまうこともあるので慎重に行ってくださいね。
左右から交互に差し込むと、均等に力がかかって開けやすくなりますよ。
輪ゴムで開ける
大きめの輪ゴムをフタの外周に巻きつけることで、手が滑りにくくなります。
滑りやすい素材のタッパーでも、輪ゴムがあるとしっかり力をかけやすくなるんです。ゴム手袋のような効果が得られるので、手の力が弱い方にもおすすめです。
ぬるま湯で柔らかくして開ける
タッパーのフタだけをぬるま湯に数分つけておくと、素材が柔らかくなってフタが外れやすくなります。
また、温度差による気圧の変化で、中の空気が膨張し密着していたフタが少し浮いてくることもあります。電子レンジ使用後に開かないときにも、ぬるま湯は効果的ですよ。
シリコン製の滑り止めマットを使う
キッチンにある滑り止めマットを使えば、フタに手をしっかり固定できて開けやすくなります。
シリコン製のものは特にグリップ力が強く、力が逃げにくくなるのが特徴です。タッパーの底にも敷けば、両手でフタに集中できてより安全です。
タオルや布巾で包んで持つ
乾いたタオルや布巾でフタを包んで握ると、手が滑りにくくなり力もかけやすくなります。
厚みのある布なら、手の負担を減らしてくれるので、固いフタでも安心してチャレンジできます。見た目はシンプルな方法ですが、意外とこれが一番効いた!なんて声も多いんですよ。
そもそも選び方が重要?タッパーがあかない原因を防ぐには

実は、タッパーがあかない問題って、そもそも「選び方」である程度防げるんですよ。
たとえば「フタの構造や素材を見極める」ことが大事。あまりに密閉性が高すぎるタイプは、しっかり保存できる半面、開けにくさの原因にもなります。
次に「密閉性が高すぎるタイプに注意」すること。パッキン付きやロック式のものは便利ですが、用途に合わないと開けにくくなることもあります。汁物用や長期保存用と、日常使いをうまく使い分けると良いですよ。
そして「パッキン付きは扱いやすさも確認」。パッキン部分が着脱できて洗いやすいか手で簡単に開けられる構造かなどもチェックポイントです。
繰り返さないために!タッパーがあかないトラブルの予防策
日常的にちょっとした工夫をするだけで、タッパーがあかなくなるトラブルはかなり防げます。
まずは「中身が冷めてからフタを閉める」ことを意識しましょう。熱いままフタをすると、冷めたときに内部が真空状態のようになってしまいます。
次に「収納時はフタと本体を別にしておく」ことで、フタがぴったり吸着してしまうのを防げます。重ねて収納するときも、軽くのせる程度にしておくと開けやすくなります。
そして「劣化したタッパーは早めに交換」することも大切です。ひび割れや変形があると密閉のバランスが崩れ、余計に開けにくくなってしまいます。
高齢者や子どもでも安心!タッパーがあかないを防ぐ工夫
家庭では、高齢の方や子どもが使うこともありますよね。そのときに困らないようにする工夫も考えておきましょう。
まずは「握力が弱くても開けやすくするには」どんなタッパーを選ぶかがポイントです。軽くて柔らかい素材、フタに凹凸があってつかみやすいものなどがおすすめです。
次に「滑り止めや補助道具の活用法」も便利。シリコン製の滑り止めシートや、フタ開け専用のグリップツールを使うと、少ない力でも開けられるようになります。
最後に「扱いやすい製品の選び方」も忘れずに。ワンタッチで開けられるものや、あらかじめ空気抜き穴がついているタイプなど、工夫された製品も多くあります。
どうしてもタッパーがあかない時の最終手段

ここまでの方法を試してもどうしても開かない…そんな時は無理せず別の手段を取りましょう。
一つ目は「専用のオープナーを使ってみる」こと。最近ではタッパー用のオープナーも売られていて、フタを傷めずに安全に開けることができます。
二つ目は「メーカーのサポートを活用する」方法。製品によっては開け方のコツや注意点が公式に紹介されていたり、問い合わせれば対応してくれる場合もあります。
三つ目は「思い切って新しいものに替える」ことも検討してみてください。無理に使い続けるより、安全で扱いやすいタッパーに替えることでストレスも減りますよ。
まとめ:タッパーがあかないイライラを家にあるもので解決しよう
タッパーがあかないというのは、意外と多くの人が経験する身近な困りごとです。
でも、ちょっとした工夫やコツを知っておくだけで、慌てずに対処できるようになります。特別な道具がなくても、家にあるものだけで開けられる方法がたくさんありますし、タッパー自体の選び方や使い方次第で予防も可能です。
身近なストレスを減らすためにも、ぜひ今回ご紹介した方法を試してみてくださいね。


